こんにちは JAYLOGです。
2020年度より学校で授業として取り組むプログラミング教育の必修化についてカンタンに説明します。
学校で取り組みが必修化されるのは知っているけど。。。
『パソコンやIT技術を使った授業で子供が慣れるのが大変そう。。』
『どんな内容なのか』
『必修化に向けて家庭でも出来ることあるのかな?』
『子供を学習サイトや教室に通わせた方がいいかな?』
こんな不安を解消していきたいと思います。
2020年度のプログラミング教育の必修化とは?

プログラミング教育とは
小学校で実施のプログラミング教育の必修化とは何かというと、論理的思考力を育てることを目的としたカリキュラムを通常の科目の中に取り込む事です。
論理的思考は、学校の科目はモチロンのこと、日常生活など、あらゆる場面で生かすことのできる汎用的な能力です。
また、問題解決や相手と円滑なコミュニケーションをとる為には必要な思考力になります。
小学校での内容や教室での授業の具体例を知りたい方はこちらが参考になります。
必修化の時期は小学校(2020年)、中学校、高校によって異なる
プログラミング教育の必修化はいつから始まるのかですが、学校によって変わります。
小学校では2020年から必修化されて全学年に導入されます。
中学校では2021年、高校は2022年から必修化されます。
ですので、今の小学生は高校まで最大12年間プログラミング教室を受けることが出来ます
ちなみに小中の学校はは全面実施ですが、高等学校では1年生から順次実施になります。
後述しますがこの教育課程で得られる能力は国語、算数など既存の科目と同じくらい重要なスキルなのですが、その一方で定着に時間がかかります。その為、小学校のうちから学校の授業として必修化して徐々にこれらの能力を伸ばしていくことが必要です。
プログラミング的思考が出来ると問題解決が出来るようになる
プログラミングを通して学ぶ思考力をプログラミング的思考と言います。この思考力は大きく『論理的思考』『問題解決能力』『創造力』の3つの能力から構成されています。
プログラムはある目的に対して物事(処理)を順序だてて考え、答えを導くために実行していくことです。その過程では様々な問題にぶつかって試行錯誤を経験して、これらの能力を学習出来るようになります。
子供が大きくなれば、今よりも多様化・複雑化した問題とぶつかることになります。そのような問題を解決できるためにも小学校のうちから必修化して問題解決のプロセスを学ぶことが肝要です。
ここら辺の内容や情報についてはこちらが参考になります。
どうして学校で必修化が必要なのか?

プログラミング教育を2020年度よりなぜ必修化にしたのかの理由は今後の社会的背景を考慮してのことです。
まずは今後AI、IoT等のICTの環境が今よりも当たり前の様に日常や社会に溶け込んできます。
その為、産業の構造自体も今よりももっとICT環境に依存してきます。これを第4次産業革命というのですが、この構造変化を迎えるにあたり、今の子供たちもICT環境やIT情報技術に慣れ親しまなければなりません。これが必修化の理由の一つです。
また、ICT環境等のIT技術が日常に溶け込むことはそれだけ多くの作り手が必要です。同様に、ICT環境の利用者もITに対する情報が求められますので需給者双方にIT人材のニーズが高くなります。
一方では人口減少でそのニーズにこたえられない状況なので、今からITに関する情報提供や知見を増やして将来的にニーズを充足したいという意図もあるでしょう。
さらに将来的には人材のグローバル化が進むため、様々な人間との潤滑なコミュニケーションが必要です。
そのためにはわかりやすく人に伝えるための論理的思考などの能力が必要ですので、今のうちからその能力を伸ばせるように授業の内容に組み込んでいきます。
必修化の背景と情報についてはこちらが参考になります。
学校での実施される目的は?

次に学校で実施される目的について説明します。
小学校での指導目的は「小学校段階で論理的思考力、創造性、問題解決能力の各種能力を育成させること」になります。
一方で『指導目的は名前の通り何かのプログラム言語も学習させるのでは?』と思う方もいらっしゃると思いますが、実はそういう内容ではございません。
なぜならIT技術は時代によって新しい言語や技術・情報が出てきたり、その技術や言語の主流は変わります。今、教育として学習したところで小学生が大人になることには陳腐化してしまうので、あまり学習効果がないからです。
これらに内容や目的についてはこちらをご覧頂きたいです。
2020年から始まる必修化の具体的な内容

小学校で取り組むカリキュラムについてです。
学習指導要領などでは具体的に決められていない
必修化の具体的に内容については決められていないので、確実に授業に盛り込むが、その内容は小学校や先生次第という現実です。この教育内容が標準化できていないというのは問題の一つです。
例えば、Aという学校ではプログラミング的思考を伸ばすことに力を入れているがBという学校では力を入れていない状態になりかねません。
今からフォローできるところは親がフォローしてあげた方がいいのではと考えています。
学校での実施内容に関する誤解と具体的な事例
まず、よくある誤解として算数や理科の様に1つの科目として存在しないです。
通常のカリキュラムの中にプログラミングを導入していくことになります。
また、実際に業務に使われているようなプログラム言語を学ぶわけでもないです。
プログラミングはその過程を通して論理的思考やをより確実に定着することを目的としており、あくまでこれらを実現していくためのツールとして使われます。
また、身の回りの機械(パソコン)の処理について考えを巡らすというパソコンなどのIT技術を使わない学習方法もあります。
具体的な授業内容についてはこちらに詳しく説明されています。
低学年では面白さを感じて高学年ではICT(情報技術)を利活用していく
最初はまずパソコンやその情報に触れて面白さを感じるということに重点を置き、高学年ではパソコンやITを利活用して学習の定着、論理的思考を育てるといったような具体例が挙げられます。
未来学びのコンソーシアム
ご家庭で取り組む場合の学習方法は無料体験や資料請求から
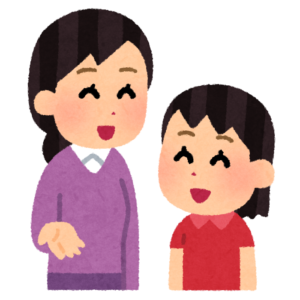
プログラミング的思考は前述したように小学生の子供の今後を考えると必要な能力だと考えています。
その教育ニーズがある一方で、その能力を育成していく教員はプログラミングに関する知識と経験が不足しており、十分にプログラミング思考を教えてあげることが出来ない可能性(または、学校によってムラがある)があります。
その問題点は私たち親も同時に抱えております。私たち先生同様にそのような教育を受けておらず、自分たちでお子様にプログラム思考を教えていくのは算数や国語と違い難しいのではと考えております。(私もその1人です)
その為、もし子供にプログラミング思考を身に着けさせたいのであれば、パソコンを使った通信教育やスクールに通わせあげた方が目的が達成させやすいです。
とはいえいきなりお金を払ってはいるのもリスクが高いので、無料体験や資料請求があるもので評判がいい講座を集めてみましたので、ご覧ください。
結構いろんなバリエーションがあるので、お子様の好みに合わせて体験をさせてあげたり資料請求をしてあげれば問題ないです。
- 体系的にプログラミング思考を学ばせたい
- それ以外の能力(プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力)も伸ばしたい
- 本格的にロボットなどの学習をさせていきたい(IT(情報技術)への親和性の高い子供を育てたい)
のであれば、プログラミング教室の無料体験を受けさせてあげることをおすすめします。
■プログラミング教室はこちらです。
■通信講座はこちらがおすすめです。
■まずは遊び感覚で取り入れてみたい方はこちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。









