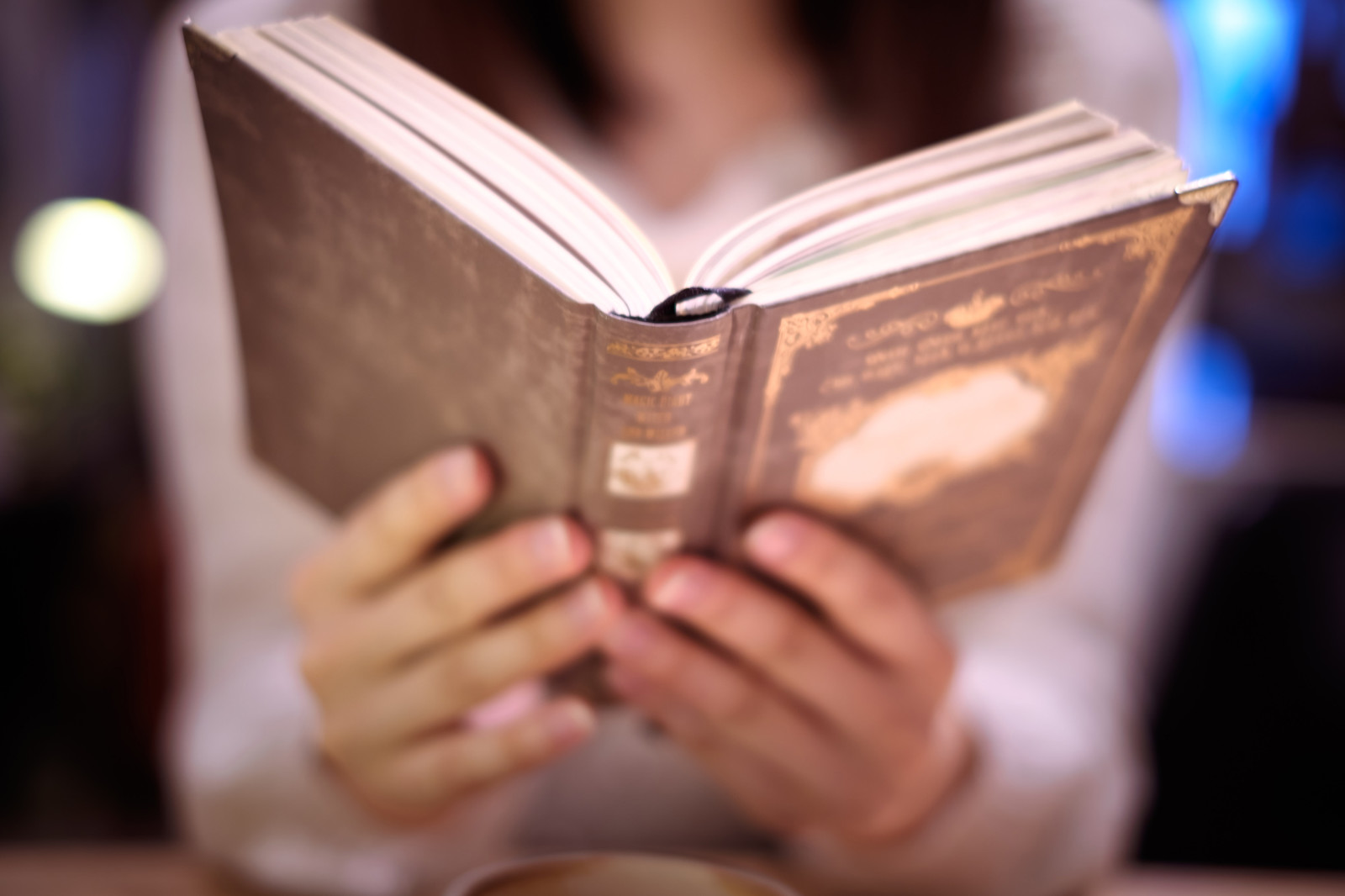こんにちは。 JAYLOGです。
今日は基本情報技術者試験(基本情報)合格に近づく為のオススメ参考書・問題集を紹介します。
参考書・問題集はそんなに重要?って思われる読者もいらっしゃるかもしれません。答えは『YES』になります。
何故なら自分のレベルに合わない参考書や問題集を選ぶことは、効率的ではないだけではなく、モチベーション低下を招くからです。途中で諦めたら今まで投資した時間が、無駄になりますからね。

この記事をで提供できる内容・・・
・自身のレベルにあった用語集、参考書、問題集がわかる。
まず、受験者層についてですが19歳〜26歳つまり大学生〜社会人4年目までとレンジが広いです。
つまり、最終的には基本情報技術者試験を受験・合格するにでもスタート地点はそれぞれ異なりますので、各々の開始レベルに合わせて書籍を紹介したいと思います。
参考書や問題集などにも売れ筋ランキングなどありますが、自分のレベル感にあったものでないと意味のないもの・もしくは効果の低いもの担ってしまいます。
ですので、自分のレベルにあった参考書や問題集を選びましょう。
まずは、基本情報技術者試験の学習開始時のレベルを定義してそのあとに参考書と問題集を紹介させていただきます。
基本情報技術者試験学習開始時のレベル感の定義
まずは、参考書をお勧めするにしても、勉強開始時点のレベルによって選ぶものがだいぶ変わってきますのでまずはそのレベルを説明します。
この後オススメする参考書と問題集にL.Xと記載するのでXはレベルに置き換えて読んでください。複数にまたがる場合は『-』で表現します。L.1-3など
| 内容 | レベル |
|---|---|
| アプリ、サーバ、回線などの実務経験がある。 | 1 |
| ITに興味があり勉強経験がある。 | 2 |
| これからITを勉強していきたい。 | 3 |
オススメな用語解説
まず、参考書を読んでも用語で躓く人には参考書と一緒に用語集が必要になります。
例えば、大学生やIT未経験の社会人、中学生、高校生あたりにオススメです。
基本情報技術者 用語集(L.3)
基本情報技術者試験に必要な用語が簡単(3-5行位)にまとめられいます。ある程度、基本情報の素養がある人には気軽に使えておススメです。
また、未経験の方は電車の中で確認するときなどに使用できます。
値段が安く対コスト効果として考えるとオススメです。
基本情報午前・合格用語キーワードマップ法+過去問451題(L.1-2)
こちらは用語解説集だけではなく著者が編み出したキーワードマップ法による解説をしており用語集としては価値のあるものになります。
因みににキーワードマップ法とは、問題の用語と選択肢にある用語を紐付けることにより回答を見つけていく方法との事です。
参考書を兼ねている用語集だと思ってもらえると分かりやすいかもしれないです、
この用語集をある程度理解できればスムーズに参考書に移行することができます。
基本情報技術者試験オススメ参考書
キタミ式イラストIT塾基本情報技術者(L.1-2)
イラストや漫画を通じて『いかにわかりやすく基本情報技術者試験の対策をしていくか?』というところにこだわりがある為、未経験の人や文章の苦手な人にとてもおススメできます。
読んでいて『なぜ?』と思うところにきちんとイラストが入っていてわかりやすいのでスッと読んでいて入ってくる参考書になります。
レベル感的には午前問題を攻略できるくらいのもので、午後対策の本は別に必要になってきます。
しかし、午後問題は午前問題という前提知識がなければ解けないため、未経験者が午前対策+午後試験へのアプローチに使うという面において優れていると思います。
やはり未経験者の方に売れているだけあってわかりやすさはNo1の参考書と言えます。
出るとこだけ!基本情報技術者テキスト&問題集(L.2-3)
試験に出題されやすい部分のみをシンプルにまとめたという参考書になり、勉強が効率的に進められるように作られている参考書です。
頻出問題中心で選択と集中がはっきり分かれているので効率のいい学習ができます。
よく過去問を研究しているなと思わせる一冊です。
ただし、イラストが少ないためある程度の知識を持った人が読み進めていかないと逆に効率的に進まないです。
もし、そのような方が使用するのであれば問題はしっかり解いていくことが大事です。
というのも、説明よりも実践にて必要な知識を習得できるように作られているからです。
(だから効率のいい参考書とも言えます。)
おススメする人は勉強時間が割けない社会人や必要最低限の学習で合格したい人にお勧めです。
基本情報技術者合格教本(L.2-3)
出題分野を全体的に網羅できている参考書です。ただある程度知識がある人が前提となっている分レベルは高めです。
分かりやすさというよりも全体的に学習したい人にはお勧めになります。
また付属の過去問ソフトCDRはジャンル別に出題する設定があり、弱点補強にかなり有効に使えます。
例えば、システムエンジニアやプログラマーには良いレベルだと思います。また、高得点を目指したい方にもいいと思います。
基本情報技術者試験オススメ問題集
基本情報処理技術者パーフェクトラーニング過去問題集(L.1-3)
これは私も使っておりオススメで問題集の定番です。
過去問のボリュームと解説量が多いのがオススメポイントです。
ボリュームも多く過去4回分の過去問が誌面で丁寧に解説されております。
また、ボリュームでいうとIPAで過去問を解いてもいいのですが、間違えた場合、『なぜ間違えたか』ということを探すのに多大な労力がかかることが多々あります。
その一方でこの問題集であれば解説がついているため、その労力が削減できるというメリットもあります。
さらに、それ以前のものはスマホでも閲覧できるので、スキマ時間でも学習できるのがメリットです。
デメリットは過去問が多いので、本来はやらないまたは重複している問題もある為自分で取捨選択をする必要があると言う点です。
基本情報技術者試験によく出る問題集【午前】(L.2)
先程は試験回別に内容が分かれてましたが、テーマ別かつ午前に的を絞った問題集となっております。
テーマ毎に頻出の問題とその度合いもわかる為、どれに力を入れるべきかが分かります。
学習をするにあたり、まんべんなくやるのも大事ですが、時間のない方は本書の様に頻出事項だけまずはつぶしていくやり方の方が、得点を取るということに関しては効率がいいです。
また、左ページに問題、右ページに解答と見開き完結型の問題集なので、答え合わせするたびに別ページを開くという煩わしさもないので、電車の中やスキマ時間でも学習できます。
実際には、この問題集で問題になれた後に実際に過去問を使って時間を測るのがオススメです。
なるべく効率よく学習したい方、自分の弱点を認識していて補強したい方にオススメです。
基本情報技術者 午前 一問一答問題集 (L.3)
こちらは、電子版のみになります。最頻出に的を絞っており、しかも安い問題集です。解説も丁寧です。(amazon ultimate会員なら実質無料です。)
電車の中で重い本を取り出さなくて良いので、電車の中で勉強する社会人には適した教材です。
問題と解答が一続きになっているので、学習効率はいいですが、ある程度理解している人でないと解説が分かりずらく感じると思います。
基本情報技術者試験の午後対策オススメ書籍
苦手分野があったり、前回午後試験で惜しくもダメだった方は弱点補強を兼ねて学習しましょう。
分野別でご紹介致します。
うかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編](L.1-2)
アルゴリズム編の書籍になります。アルゴリズムを苦手としてる人は多く実際にテストで捨てる人もいます。(私もそうです。)
この参考書はイメージと対話形式で作られており、内容もプログラミングから離れた身近な例からアプローチしているので、取りくみやすいです。
また、過去10年分の基本情報技術者試験で出題されたプログラムを実際に動作させて解説しているサイトがあり、過去問を解いていてイメージできなかったところがビジュアルで理解できる点においてこの本は優れています。
基本情報技術者 試験によくでる問題集【午後】(L.1-3)
3-2で紹介した本の午後対策用になります。頻出問題をテーマ別に構成していて、解き方や注意点を記載しているどちらかというとテクニック問題集になります。問題数も50問と豊富ですので、これを一通りやれば午後対策の全般は網羅できます。
本書を購入するのであれば、午前問題もセットにした方が効率はいいです。
すっきりわかるJava入門(L.1-2)
午後のプログラム言語の勉強におすすめの書籍になります。Javaの基礎からオブジェクト指向までイラストメインで勉強できる問題集になります。
また、スマホからでもコーディング、コンパイルができる環境があり、どこでもjavaの実践的な学習ができます。(業務などでも使用できる)
言語の章でも記載しているのですが、言語は参考書だけ見ていても理解できません。
実際に手を動かしてコーディングしてみたり、トレースしてみたりする経験が豊富にないとなかなか問題が解けないというものです。
本書は、そういう点で他の問題集より学習スピードが速くなるという利点があります。
この本は今後Javaを組む技術者や新入社員研修でjavaを学ぶ予定の学生さんにとっては、資格取得以外に実用書としての側面もあり、おススメできます。
さいごに
どんな試験にも共通して言えるのが『自分のレベル』、『確保できる学習時間』にあった参考書や問題集を選ぶ必要があります。本記事を通してご紹介させていただいた組み合わせで合格に貢献できれば幸いです。